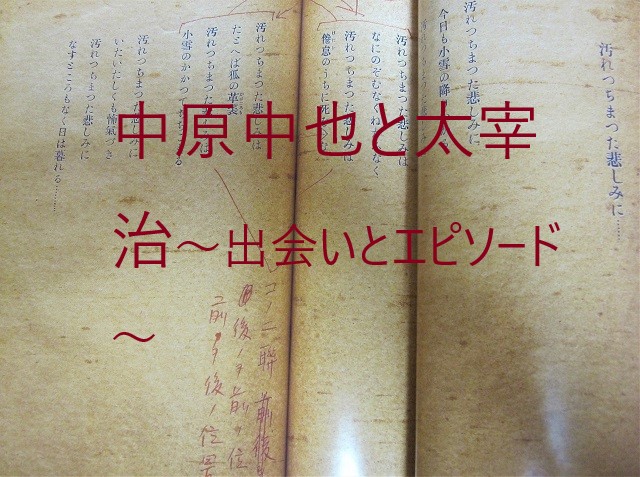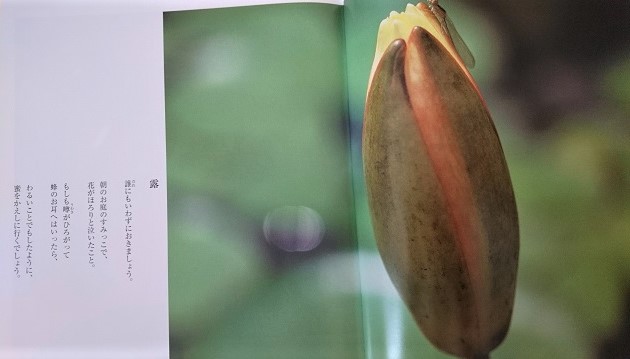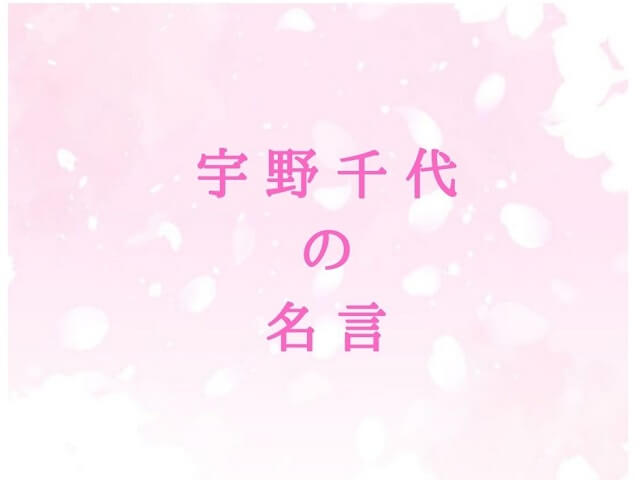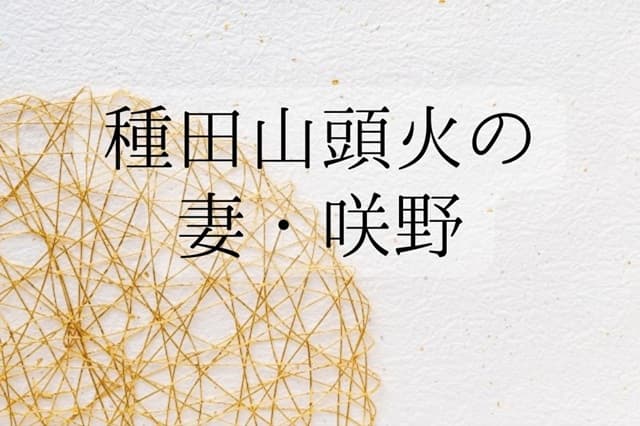
自由奔放な放浪生活を続け、「分け入っても分け入っても青い山」などの名句を数多く残した孤高の俳人・種田山頭火。
その生涯は多くの人々に知られるところですが、彼の奔放な旅を支えた続けた妻・咲野(さきの)の存在はあまり知られていません。
山頭火が世捨て人のように自由な放浪生活を続け、創作活動に専念できたのは、咲野さんの支えがあってのことでした。
彼女なくして、山頭火の文学は成り立たなかったといっても過言ではありません。
周南市(旧佐波郡和田村)の裕福な旧家から種田家に嫁いだことをきっかけに、波乱に満ちた人生を送ることになった咲野さん。
明治、大正という封建的な価値観が色濃く残っていた時代の中、妻として、母として一家を支え、離婚後も山頭火を支え続けました。
この記事では、山口県にゆかりのある種田山頭火の妻・咲野さんの、放浪の俳人を支え続けた、愛と苦悩に満ちた生涯をご紹介します。
※山頭火(本名・種田正一)は、自由律俳人として活動した際の号です。この記事ではわかりやすさのため「山頭火」で統一しています。
山口の旧家から種田家へ・咲野さんと山頭火の結婚
周南市の旧家で育った咲野さんの人物像
咲野さんは現在の周南市高瀬(旧佐波郡和田村)の大地主の佐藤家に生まれました。
こんにゃく玉栽培が盛んだった地域で、実家は大変裕福だったそうです。
幼い頃から美人でおとなしく、気立ての良い女性として知られていました。
当時はあまり進む人がいなかった、尋常高等小学校の高等科に進学し、防府市宮市にあった周南女紅学校へ進学。
寄宿舎生活を送りながら、技芸を学びました。
山頭火の実家・種田家

山頭火の生家・種田家は、防府市宮市に代々続いた大地主で、山頭火はその長男でした。
幼少期はとても裕福な暮らしを送っていたそうです。
しかし、11歳の時に母フサが自殺。
この時を境に一家の歯車が狂い始め、父・竹治郎の放蕩によって種田家の財政は傾き、早稲田大学に通っていた山頭火の授業料も払えなくなるほど困窮します。
山頭火は授業料未納と神経症発症により大学を中退。志半ばでの帰郷を余儀なくされました。
山頭火との出会いと結婚
帰郷後およそ2年の間、山頭火と咲野さんは、隣同士で生活していたといいます。
咲野さんが学んだ学校の寄宿舎が、種田家と小さな川を挟んですぐそばにあったためです。
この間に咲野さんは、山頭火の父・種田竹治郎に見初められます。
財政が傾きつつあった種田家にとって、裕福で人柄のよい娘との縁組は、とても魅力的だったのでしょう。
咲野さんが学校を卒業した年、種田家は人手に渡り、一家は大道村に移って「種田酒造場」として再出発を図るために引っ越し。
その後、竹治郎が咲野さんの実家・佐藤家に縁談を持ち込み、明治42年に結婚します。
咲野さん21時、山頭火28歳。お見合いらしい見合いはなかったそうです。
しかし、文学にのめり込む夫と道楽好きな舅との新しい生活は、想像以上の苦労の連続でした。
種田家の没落、家族の離散
突然の破産と家庭の崩壊
結婚から一年後、長男・健(たけし)が誕生します。
子どもが生まれ、家庭は安定したように思えましたが、そんな生活は長続きしませんでした。
大正5年、「種田酒造場」が倒産します。
咲野さんの実家から融資を受けて仕込んだ酒蔵の酒が、2年続けて腐ってしまい、資金繰りが立ち行かなくなって多額の借金だけが残されました。
さらに、父・竹治郎が夜逃げして行方知れずに。
残された山頭火はなんとか酒造場を再建しようとしますが、商売の才覚に乏しく、一家は大道を追われます。
熊本での再出発、咲野さんの奮闘
心機一転、熊本へと移り住み、文学仲間の協力を得て、古本屋「我楽多(がらくた)書房」を開業します。
開店資金などはすべて、咲野さんの実家が工面してくれたものでした。
しかし、山頭火は行商に出るものの売上は店に入れず、逆に店のお金を持ち出して文学仲間と飲み歩く日々。
そのため自然とお店の切り盛りは、咲野さんの肩にのしかかっていきました。
倒産、夜逃げ、夫の放蕩…。咲野さんが心に抱いていた不安は計り知れませんね。
山頭火の出奔と戸籍上の離婚
大正7年、山頭火の弟・二郎が、岩国の山中で自殺。
母の死、倒産、父の出奔、弟の死。
家族の不幸が続いた影響もあり、山頭火はますます深酒と自暴自棄に陥っていきました。
さらに、文学仲間が相次いで上京してしまい、寂しくなった山頭火は妻子を置いてふらりと上京。
この行動を知った咲野さんの実家は大激怒し、山頭火のもとに離婚届を送り付けました。
山頭火は深く考えず、押印して返送。
これを見た咲野さんは、離婚を決意します。
しかし、実家にはこれまで通りに生活させてほしいと懇願。
実家に戻ることなく、一家の大黒柱として、自立した女性として、生きることを決意したのです。
熊本での商売は軌道に乗り、息子と二人で生活できるほどになっていました。
咲野さんは商売上手で、お店を訪れる学生たちに、当時は珍しかったコーヒーをふるまっていたそうですよ。

離れても続く絆・咲野さんが支え続けた山頭火
関東大震災で帰郷した山頭火
山頭火は東京で仕事に就いたものの、神経衰弱で退職。
行商をしながらそのまま東京に留まるも、大正12年の関東大震災で被災します。
混乱の中、鉄道会社が乗客を無賃乗車させてくれたのをよいことに、熊本へ戻ったのでした。
離婚した咲野さんの元へ戻ることもできず、とはいえ、自然に咲野さんのもとに足が向いてしまう山頭火。
自分たちを置き去りにして、数年行方をくらましていた人をすぐに家に入れてくれるほど、咲野さんは甘くありませんでした。
行く先がなくなった山頭火は、文学仲間のところに転がり込み、ふたたび酒浸しの日々を送り始めます。
咲野さんから家の敷居をまたいでもよいと許しが出たのは、翌年のことでした。
出家と、咲野さんに手渡した聖書
その年の暮れ、泥酔した山頭火が電車を急停車させる騒ぎを起こし、寺に連れて行かれます。
そこで住み込みとなり出家し、行乞の道に入ることとなりました。
咲野さんが寺を訪ねると、山頭火は聖書を手渡しました。
女一人での生活は大変で、何か頼るものがないとやっていけないだろう、との思いから手渡したのでは思われます。
咲野さんはこの聖書をきっかけに教会に通い、洗礼を受けました。
この時、山頭火44歳、咲野さん37歳、息子の健は15歳でした。
咲野さんあってこその山頭火
夫婦という形を超えた支え

行乞の旅に出たあとも、山頭火は何かにつけて咲野さんのもとを訪ねました。
咲野さんの元へ戻るものの、数か月すればふたたび旅へ出てしまうのですが。
山頭火は咲野さんとの関係を「逢ったところでどうなるのでもないが、やっぱり逢いたくなる。私と彼女との交渉ほど奇妙なものはない」と記しています。
山頭火は咲野さんを気心のしれない相手として慕い、咲野さんも山頭火をことをよくわかっていました。
咲野さんは山頭火にお金や物品の援助をしたり、息子・健の将来について相談したり。
戸籍上は離婚していても、見えない部分で通じ合っていたのです。
咲野さんの晩年
山頭火の死後も、咲野さんは故郷に戻ることなく、熊本で生活を続けます。
昭和43年、80年で波乱万丈の生涯を終えました。
山頭火の長い放浪生活の陰には、咲野さんの静かな支えがありました。
行乞の旅に出られたのは、生活を咲野さんが引き受け、息子・健の成長を守り続けてくれたからです。
夫婦としての縁は切れても、その“見えない土台”が、山頭火の自由な放浪と俳句創作を可能にしたことは間違いありません。
咲野さんの略歴
- 明治22年 周南市高瀬の佐藤家に生まれる
- 明治37年 周南女紅学校に入学
- 明治42年(21歳) 種田正一(山頭火)と結婚
- 明治43年 長男・健が誕生
- 大正 5年 種田酒造場が倒産、熊本へ移り住む
- 大正 9年 戸籍上の離婚(生活上の交流は続く)
- 大正14年 山頭火出家
- 大正15年 山頭火行乞の旅に入る
- 昭和15年 山頭火、松山の「一草庵」で死去
- 昭和43年 熊本で逝去(享年80)
まとめ
放浪の詩人・山頭火の妻「咲野」さんをご紹介しました。
ほとんどお見合いもないままに種田家の嫁ぎ、酒造場の倒産、父と夫の夜逃げ、夫の泥酔、出家など、波乱の連続だった咲野さん。
しかしその人生からは、自分の軸を曲げることのない、強さとしなやかさを感じることができます。
離婚をしたものの実家に帰ることなく、ひとりで子どもを育て、山頭火を支え続けたことからも、咲野さんの並外れた芯の強さを感じられます。
地に足の着いた彼女の存在は、山頭火の孤独な放浪の旅の中の「拠り所」だったのでしょう。
山頭火の文学を語る上で欠かせない、影の立役者が咲野さんであったといえます。
咲野さんの存在を知ることで、山頭火の句や旅も、より興味深く感じられるのではないでしょうか。
- 『種田山頭火の妻「咲野」』 田村悌夫/山頭火ふるさと会
- 『防府の生んだ自由律俳人山頭火』防府市文化協会