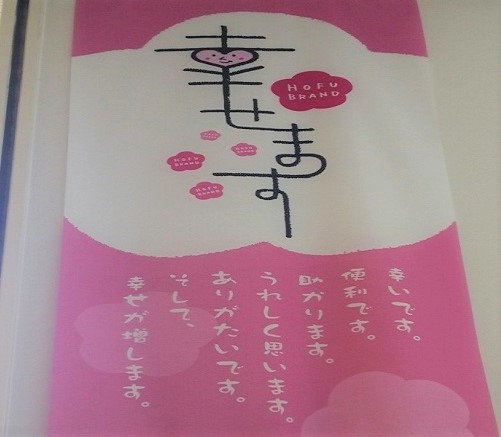「さばる」という方言をご存じでしょうか?
ある日、 山口県は宇部市在住の妹が、宇部で使われる方言「さばる」を教えてくれました。
妹によると、宇部ではもたれかかることを「さばる」と言うらしいのです。
本当に宇部で使われているのか、山口県内の他の地域では使われていないのか、山口県外ではどうなのか、気になって調べてみました。
どうやら「さばる」は、宇部で使われているのとは違う意味の方言として、岡山や島根でも使われているとのこと。
とても不思議ですよね。
そこでこの記事では、「さばる」がどこで使われているのか、その意味、、地域で異なるニュアンスをまとめてみました。
※「さばる」がどこで使われているか、またその意味については、スレッズでいただいたコメントを参考にまとめました。
「さばる」ってどんな意味?まずは基本を解説
「さばる」は、山口県(宇部周辺)をはじめ、岡山県や島根県の一部で使われている方言です。
大まかにいうと、「何かにくっつく」「寄りかかる」という動作を表しますが、地域によってそのニュアンスが大きく異なります。
基本となる意味を、使われている地域別で確認してみましょう。
【山口県】「さばる」は宇部周辺限定!? 意味と使い方
調べてみたところ、山口県内で「さばる」が使われているのは、宇部・山陽小野田・下関(山陽側の一部)でした。
下関(山陰側)、県央、県北部、県東部では、使われておらず、宇部・山陽小野田周辺でのみ使われる方言のようです。

宇部周辺では「背中を寄りかからせる」「もたれる」ことを「さばる」というらしく、同じように「寄りかかる」を意味する方言「すがる」と同様に使われるようです。
ただ、「さばる」と「すがる」では少しニュアンスが違うそう。
実際に使う人でないとわからないニュアンスの違いがあるのですね…。
★そんなところにさばっちゃいけんよ(寄りかかったらだめよ)
★机にさばる(机に寄りかかる)
【岡山・島根】「さばる」は山口と意味が違う?
「さばる」は、宇部周辺から離れた岡山、島根でも使われています。
ただし、岡山や島根で使われる「さばる」は、宇部で使われる意味と少し異なっています。
岡山の東南部(岡山市、倉敷市など)、島根県の松江や出雲で使う「さばる」は、「くっつく」「まとわりつく」「つかまる」を意味するそうです。


似たような意味のようですが、「つかまる」はしっかりとした動作、「寄りかかる」は疲れた時などのふわっとした動作という違いがあるように感じます。
★蚊がさばりついてくるけえなあ(蚊がまとわりついてくるからな)
★柱にさばる(柱につかまる)
「さばる」の語源は古語にあり?
地域によって「寄りかかる」「つかまる」と意味が違う「さばる」。
方言研究では、古語の「さはる(障る)」に由来するという説が有力とされています。
古語の「さはる」は「邪魔になる」のほかに「触れる・接触する」という意味も持っていました。
- 山口の「もたれる・寄りかかる」⇒「(邪魔なものに)触れて(頼って)寄りかかる」というニュアンスから派生。
- 岡山・島根の「まとわりつく・つかまる」⇒古語「さばる」の「触れる・接触する」という意味が強調されて変化。
まとめ
方言「さばる」についてご紹介しました。
「さばる」という同じ音の言葉なのに、「寄りかかる」と「つかまる」のように、地域によって動作のニュアンスが異なるのはとても不思議ですよね。
この「さばる」の語源は、古語の「さはる」にあるという説が有力です。
今では宇部周辺など限られた地域でしか耳にしない言葉かもしれませんが、一つの古語が長い歴史の中で、その地域の人々の生活や感覚によって異なる意味に変わっていったのだと考えると、とても面白いですね。
山口県はもちろん、岡山や島根を訪れる機会があれば、ぜひ「さば」という言葉を探してみてください!
■山口県や九州、四国で使われる方言「きびる」とは?
⇒方言「きびる」は山口だけじゃない!!九州・四国・広島での意味と使い方をご紹介