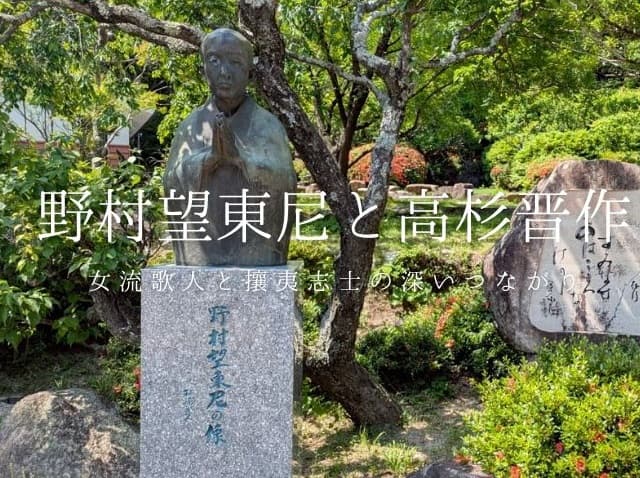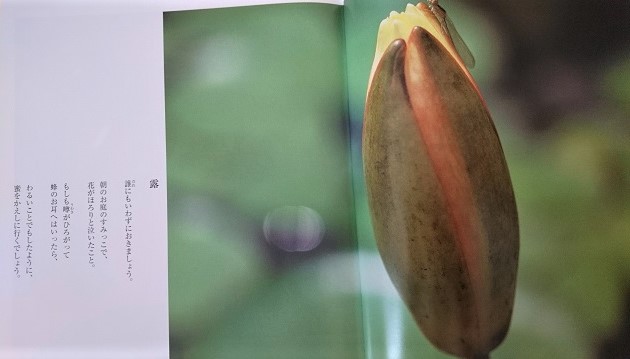山口市生まれの日野原重明(ひのはら しげあき)さんは、105歳まで現役で医療現場に立ち続けた医師です。
「病院は、神の愛によって患者の苦しみを癒す場所である」という、聖路加病院の理念に込められた思いを大切に、心から患者に寄り添う医者であり続けました。
また、患者のための「予防医療」に尽力し、医療従事者の教育制度を確立するなど、日本の医学界に数々の功績を残した人物としても知られています。
「命の大切さ」や「生き方」について語った言葉は、名言として今なお多くの人を勇気づけています。
この記事では、日野原さんの功績や名言、命の大切さを伝え続けた生涯について紹介していきます。
日野原重明さんはどんな人?
信念と医学への道
日野原さんは、キリスト教メソジスト教会の両親のもと、山口の地で誕生。
キリスト教の愛と奉仕の心を土台に、「神さまから与えられた“かけがえのない時間が命である”。それをどう使うかが“生きる”ということ」という信念が育まれました。
医師を志したのは10歳のとき。病気の母を献身的に看病する医師の姿に感動したことがきっかけでした。
関西学院中学部時代には、聖書の「よきサマリヤ人」の話に感銘を受け、「人として平等に、病に苦しむ人のために私の生涯を捧げよう」と心に決めたそうです。
アメリカ医学の祖といわれるオスラー医師の文献との出会いから、「医療の対象は”病”ではなく”人”である」とし、常に患者に気を配り、寄り添いました。
聖路加国際病院の医師になってからアメリカへ留学。「医師と専門スタッフが連携するチーム医療の体制に衝撃を受けた」と語っています。
帰国してからは、その学びを活かし、日本の医療制度や教育体制の改革につとめました。
また、1970年の「よど号ハイジャック事件」で人質となり、死を覚悟した経験から、「これからの人生は誰かのために奉仕しよう」と決意。この時から医師としての出世よりも、人や社会のために尽くす道を歩み始めたのです。
医師として「病む人の心に入り込み、患者とともに問題を解決することが最も大切」。この信念をもって現場に立ち続けた日野原さんは、患者からも医療従事者からも厚い信頼を寄せられました。
病を経験して、音楽と癒しの世界へ
105歳の長寿を全うした日野原さんですが、ご自身も病気に苦しんだ経験が何度かありました。
「家族や自分自身が病気で苦労した経験が、目の前の患者と向き合う中で役に立った」と、語られています。
音楽との縁も、きっかけは病気でした。
ピアノを習い始めたのは、急性腎臓炎で療養した小学校4年生のとき。
京都帝国大学(現・京都大学)1年生で結核療養したときには、レコードを聴きながら楽譜を起こす練習をしたそうです。
のちに「全日本音楽療法連盟」の理事長を務めたり、ミュージカルの企画や脚本にも関わるなど、音楽の力で心を癒す活動を広げました。
晩年まで現役で活動
日野原さんは晩年まで医師として働きながら、講演、執筆、音楽活動にも取り組んでいました。
88歳より、「生き方上手」の連載を通じて中高年世代にエールを送り、高齢者が社会で元気に暮らせるように「新老人の会」(75歳以上の自立した高齢者の会)を立ち上げています。
生涯で300冊以上の著書を執筆した日野原さん。
105歳で亡くなるおよそ半年前に、インタビュー形式で遺された言葉が、最後の著書『生きていくあなたへ』(幻冬舎)につづられています。

日野原重明さんの功績
予防医学の普及と日本の医療・社会への貢献
「病気になってから治す」のではなく、「病気にならないように生きる」ことの大切さを伝えた日野原さん。
1954年、聖路加国際病院に民間病院として初めて人間ドックを導入。病気の早期発見と予防の重要性を広めました。
「成人病」という名称を「生活習慣病」へと言い換え、「年齢のせいで病気になるのではない。生活習慣を見直せば防げる病気もある」と訴えました。
この考え方は、国民の健康意識向上や食事・運動の改善につながり、日本の予防医学の基盤を築きました。
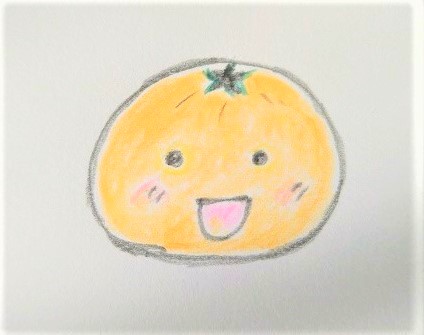

日野原さんは、内科医として最初に担当した少女の死によって、「心と体のケア」の必要性を痛感。終末期医療において「患者の心身のつらさを和らげたい」との思いから、1993年に日本初のホスピス「日野原記念ピースハウス病院」を開設しました。
また、1995年の地下鉄サリン事件では、聖路加病院に搬送された640人のうち1名(搬送時に心肺停止状態だった)を除いて、全員が後遺症なく回復。当時医院長だった日野原さんの適切な判断と指揮、災害時も対応可能な病院設計やスタッフの育成が実を結ぶ結果となりました。
現役医師としての姿勢と社会活動
105歳で亡くなる数カ月前まで、日野原さんは毎日スーツを着て病院に出勤し、病棟を回って患者に声をかけていたそうです。
「患者の目を見て話し、安心してもらうことが大事」と、常に実践を通して後進の医療従事者に手本を見せていました。
また、平和を望む大人を育てることを目的に、全国の小学校で「いのちの授業」を行い、命とは「自分の使える時間」であること、和解の一歩は「相手の気持ちにも気づくこと」だとして、「ゆるすこと」の大切さを語り続けました。
1995年には、「全日本音楽療法連盟」の初代理事長に就任。音楽による癒しの力を医療に取り入れ、演奏活動や療法の普及にも努めました。
さらに、命について描かれた絵本『葉っぱのフレディ』のミュージカル化に協力し、自らも出演。子どもたちに命の大切さを伝え続けました。

日野原重明さんの名言・伝えたかったこと
「命とは君たちが持っている時間である」
これは、小学生への「いのちの授業」でよく語られていた言葉です。
「”命”というものは目に見えないけれど、それは”自分に与えられた時間”である。時間をどう使うかを考え、自分のためだけでなく、誰かのために使うことを学んでほしい」と伝えました。
戦争やハイジャック事件で、死を覚悟した経験を持つ日野原さんだからこその切実な思いであり、ご自身も他者や社会に貢献する生き方を貫きました。
「生かされている最後の瞬間まで、人は誰でも『人生の現役』なのですから」
年齢に関係なく、人は常に「今」を生きている。「もう年だから」ではなく「今できること」を考えて生きることが大切だと説いたことばです。
日野原さんは、高齢者が自信を失わずに、社会の中で自分の人生を自分らしく生き続けることを強く願い、支援していました。
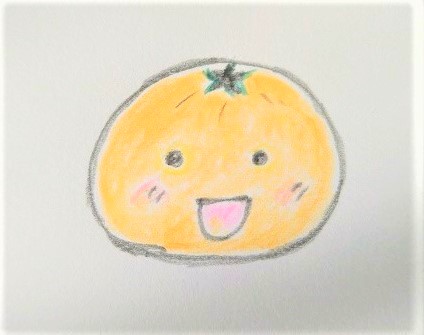
「『ありがとう』のひと言は、残される者の心をも救う、何よりの遺産です」
医師として、多くの「死を迎える人とその家族」を見つめ続けてきた日野原さんの、”気づき”ともいえる言葉です。
死んだら地位はなくなるし、財産を残しても争いの種になる。けれど、「ありがとう」「大好きだよ」といった言葉は、遺された人の心を救う財産としてずっと残る。
「納得できる死とは、最期にありがとうと言って、死ねるかどうかだ」とも語っていた日野原さん。ご自身も、ご家族や周りの方へたくさんの「ありがとう」を遺して最期を迎えられたそうです。
日野原重明さんの略歴
1911年(0歳):母の実家がある現在の山口市湯田温泉で、6人兄弟の次男として誕生
1915年(4歳):家族とともに神戸へ引っ越す
1918年(7歳):キリスト教の洗礼を受ける
小学生時代:病気で学校を休んでいたとき、母の勧めでアメリカ人の宣教師の奥さんからピアノを習う
中学生時代:弁論部に入部。人前での話下手を少しずつ克服
高校生時代:家庭教師をしながら勉強。詩やエッセイを書いたり、友人との音楽活動を楽しむ
1932年(21歳):京都帝国大学医学部に合格
大学時代:結核にかかり、1年間療養生活
1941年(30歳):聖路加国際病院に内科医として勤務
1942年(31歳):教会の日曜学校で教師をしていた女性と結婚
1951年(40歳):アメリカのエモリー大学に留学。予防医療や患者中心の医療を学ぶ
1954年(43歳):日本で初めての人間ドックを開設
1970年(58歳):よど号ハイジャック事件で人質となる
<これからの人生を人のために使おうと決意>
1973年(62歳):ライフプランニングセンターを設立
1992年(81歳):聖路加国際病院の院長となり、病院の新しい建物の建設を指揮
1993年(82歳):日本初の独立型ホスピス「日野原記念ピースハウス病院」開設
1995年(84歳):地下鉄サリン事件で多くの被害者を救助
2000年(89歳):「新老人の会」を結成し、高齢者が元気に社会参加することを応援
2001年(90歳):著書『生きかた上手』がミリオンセラー
: 日本音楽療法学会の初代理事長に就任
2011年頃(100歳)~:主に小学校4年生を対象に「いのちの授業」開始
2017年(105歳):自宅で家族に見守られながら永眠
まとめ
日野原重明さんの生き方や功績、名言についてご紹介しました。
日野原さんにお目にかかる機会はありませんでしたが、「山口ふるさと大使」として県内でも何度か「いのちの授業」が行われたと知り、親しみが増しています^^
この記事を書くにあたり、たくさんの日野原さんの言葉やエピソードに触れ、とても元気づけられ勇気づけられました。
「目に見えない命や心、言葉を大切にしよう」
「生かされている最後の瞬間まで、人は『人生の現役』。“今”を生き、誰かのためにできることをしよう」
そのように生きぬいた日野原さんのメッセージは、温かく深く心に響き続けています。
ここでのご紹介はほんの一部でしたが、人生のエールともいえる、日野原さんの言葉やエピソードとの出会いのきっかけとなりましたら嬉しいです^^