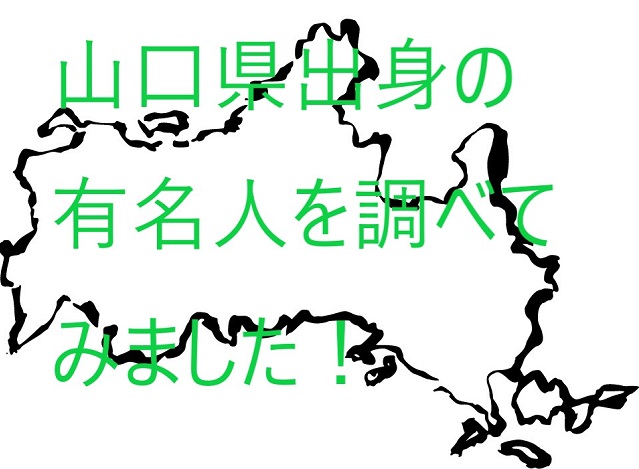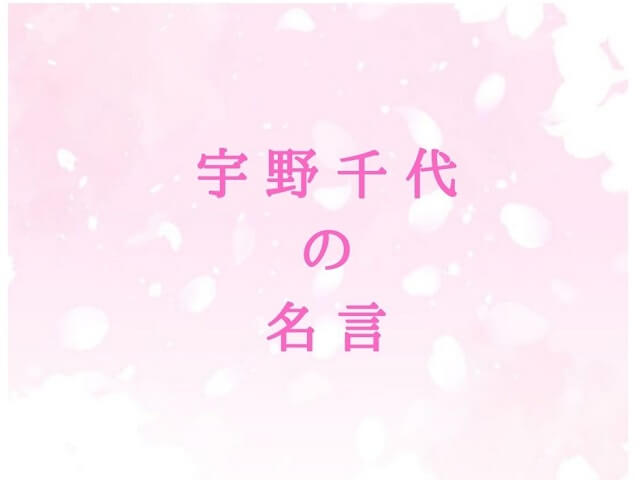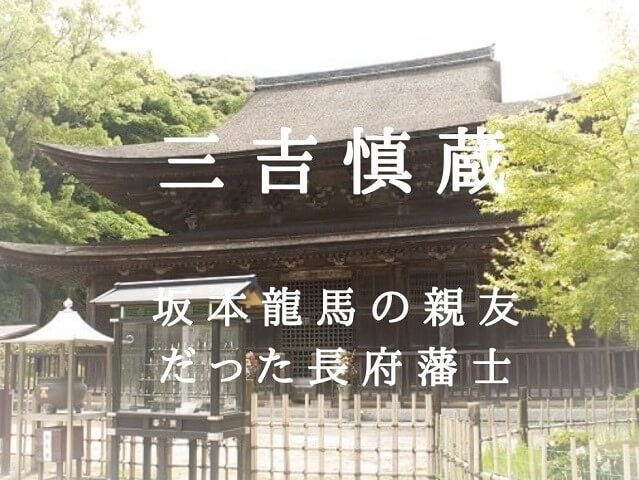「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」と評されたほどの行動力で、奇兵隊創設や四境戦争など、脱兎のごとく活躍した長州藩士・高杉晋作。
彼による下関の功山寺挙兵がなければ、明治維新は数年遅れただろうといわれるほど、幕末の動乱の時代に大きな影響を与えた人物です。
そんな高杉晋作は、生前多くの名言を残しました。
今を生きるわたしたちに勇気を与えてくれる言葉や、あの高杉晋作でもこんな言葉を呟いたのだな、と少しほっとできるような言葉たちです。

高杉晋作の名言

その生涯のいかなる時も、父の言葉は、つねに胸にあったのですね
同じく、田中光顕へあてた書簡に記された言葉。
「人間としての正しい生き方は、昔のよしみを大切にする事」との意味です。
江戸遊学中の言葉。遊学を希望する想いが溢れています。

藩主の前で、奇兵隊結成を宣言しました!
師である吉田松陰と同じく、萩城下の野山獄に投じられた晋作。処刑された吉田松陰を偲んで、投獄初日に詠んだ句です。
師・松陰の志を継ぎたいという思いが高まり、晋作は、獄中でも書を手放しませんでした。

野山獄投獄中に記した『投獄日記』より。
器用に生きられない晋作は、晋作が少年の頃に読んだ書物の中にあった、「利発な人よりも愚者になれ」という教えに励まされてきました。
功山寺での挙兵にあたり、三条実美や五卿を訪ね、出された酒を飲み干して言った決起の挨拶。

兵力に絶望的な差がある、決死の覚悟での挙兵でした
幕府との戦の前、奇兵隊を鼓舞するために発した言葉です。
病に倒れ、床に伏した晋作を見舞いに来た、井上聞多と福田侠平に向かって言った言葉です。
最後の最後まで、日本の行く末を気にかけていました。
病が重くなり、すべての職を退いた後に残した言葉。
目まぐるしく動く時代に取り残されていく寂しさを詠った、といわれています。
辞世の句「おもしろきこともなき世をおもしろく」
辞世の句ではなかった?
晋作が死の床で「おもしろきこともなき世をおもしろく」と上の句を詠んだものの続かず、最期を看取った野村望東尼(のむらぼうとうに)が「すみなすものは心なりけり」と下の句を詠むと、晋作が「おもしろいのう」と呟き、息をひき取った。
晋作の辞世の句に関しては、このようにいわれてきました。
しかし近年、この歌が詠まれたのは1866年の暮れで、晋作が亡くなる4か月前とされています。
厳密にいえば、辞世の句ではないということですね。
不満を詠った句だった?
また、もともと晋作が詠んだのは「おもしろきこともなき世におもしろく」であり、「世を」としたのは、のちの改作であるともいわれています。

晋作の辞世の句「おもしろきこともなき世をおもしろく」は、「このつまらない世の中をおもしろくしてやろう!」という晋作の破天荒な性分が伝わり、聞いたらなんだか元気が出てきますよね。
わたしもずっと、そう思ってきました。
ところが、「世を」を「世に」に変えるとどうでしょう。
「こんなつまらない世の中、おもしろくなかった」という不満にもとらえられるのです。
武士の家に生まれた晋作は、藩や国が危機にさらされているのを黙って見過ごすことができませんでした。
本当はもっと、違った生涯を送りたかった。
その思いが、死を前にしてこのような上の句を詠ませたのだともいわれています。
上の句を引きついだ望東尼は、それはその人の心の持ち方次第である、と諭すような下の句をつけています。
「おもしろきこともなき世におもしろく」。
句を詠んだ晋作の真意は今となってはわかないところですが、読む人の心情によっても、捉え方がかわるのではないでしょうか。
高杉晋作とは

高杉晋作は、戦国時代から毛利家に仕える家臣の家に生まれました。
今でいうエリートの家系です。
藩校明倫館に通い、剣術修行に励んでいた晋作でしたが、19才の頃吉田松陰と出会い、親に内緒で松下村塾に入塾。その志や日本の将来を憂う先見性に大きな影響を受けました。
24才の頃、アヘン戦争敗北後の上海へ行き、中国人が欧米列強に支配されている様子を見た晋作。
日本の将来に危機感を抱くと、帰国後、藩の同志とともに英国公使館を焼き討ち。過激な攘夷活動を展開します。
1863年、長州藩は攘夷を決行し、関門海峡にて外国艦を砲撃しますが、反撃を受け惨敗(下関戦争)。
晋作は下関の防御を一任されると、外国からの砲撃に備えるため、武士階級以外でも「志」があれば入隊できる奇兵隊を結成。初代総督を務めました。
急進的な攘夷運動のため朝敵になった長州藩は、藩内が俗論派(保守派)と正義派(攘夷派)に分裂。藩内は混乱を極めます。

幕府による第一次長州征伐が迫る中、晋作は分裂した藩内を統一するために、功山寺にてわずか80人の同志とともに挙兵。
奇策により勝利をおさめ続け、藩内を武備恭順に統一し、藩の実権を掌握します。
しかし、晋作の身体は病魔に蝕まれていました。
1867年、下関の桜山にて肺結核の療養中、29才(満27才8か月)の若さで亡くなりました。
まとめ
高杉晋作の名言と辞世の句、生涯をご紹介しました。
晋作が残した言葉に、励まされたり、共感したりする部分もあったのではないでしょうか。
豪快に、破天荒に幕末を駆け抜け、日本を新しい時代へ導いた高杉晋作。
生まれた時代が違っていたら、どんな夢を持ち、どんなことを成し遂げたのでしょうね。
高杉晋作の功山寺挙兵については、こちらの記事で詳しく書いています。あわせてどうぞ。
高杉晋作が挙兵し、幕末の歴史を動かした始まりの地です。